和歌詠みのススメ #0 序文
忍世 仮名
和歌とは
古文の授業で扱う文章では、しばしば歌が登場する。
和歌と呼ばれるそれは、平安時代をはじめとした古の日本に住む人々のやりとりであり、そして、たった31文字に趣き(情緒)や、奥深い意味を込めた詩でもあるのだった。
和歌ーーそれは季語を以てわびさびを表現する俳句とも異なり、或いは現代の自由な形式を求める(現代)短歌とも違い、風流さ、そして掛詞や枕詞などの"ことば"の意匠が織り込まれた、区別して「和歌」と呼ぶに値する一つの詩形式であるのだと。
そして、そんな和歌という文化に浸かって、ひそやかに自分たちで和歌を詠んで活動をしている人たちがいるのである……
懐古「この活動の起源について」
和歌詠み部。
このブログを訪れてくれている人の中には、外部リンク集の中に妙なものがあるのに気付いた人もいるかもしれない。
個人ブログへのリンクが多い中で、たった五文字。"わかよみぶ"。これはいったい何なのか。
話は、遥か数年前にまでさかのぼる。
当時高校生だった私ー筆名・忍世 仮名ーは、古文の小テストで余白に和歌を書いていた。それがすべての始まりであった。その授業ではしばしば和歌創作の課題などが公示されており、この先生ならば小テストの余白欄に書いた和歌であっても何か反応してくれるかもしれないー幼心1にもそう思った私は、十点満点の小テストをできるだけ急いで終わらせて、これまた古文の授業前の十分休みに大急ぎで文法書とにらめっこして作った和歌を暗記しては余白に書いてみたのである。
想像以上だった。
先生は、コメントをくれるどころか返歌を考えてくれたのである。
その日から私にとって古文の授業は和歌を書くための発表の場となり、古文の前の休み時間は和歌を作る時間となった。
小テストは(10点満点を目指してしかるべきのその点数はそこそこに)先生へ和歌を送るための手紙と化し、返歌を受けてのまた別の歌を、ということが何度か続くうちに、先生と私の和歌やり取りはすっかり習慣となっていたのであった。古文を控えた十分休みには、友達の席にもいかずに文法書や単語帳を片手にノートに歌の候補を書いては吟味し、推敲していたのを覚えている。
やがて私の詠み活動はエスカレートし、そのうち定期考査のテストや実力テストでも余白に(その時に出た問題文のあらすじに即した)和歌を書くようになったのだが2最終的に私は理系に進み、そして当然ながら高校三年生では受験勉強に追われ、受験競争という名の戦争の中においては和歌などという文化的活動は抑圧されるばかりで、私はやがて和歌詠みから遠ざかっていった……3
京都での大学時代
やがて私は京都の大学に進学したのだが、卒業してしばらく経ったある時、母校を訪れることになる。
その時、私は知ることになるのだった。「先生」がもはや古文の先生ではないのだということを……
それは、私が自らの和歌詠み活動をサークル化しようと決意した大きなきっかけだった。
さりとて、サークルを名乗るのは勝手4だがそれには志を同じくする人々ーー活動仲間がいなくてはならない。むろん個人サークルという概念もあるが、大学でやるからにはやはり(大学)サークルらしく、学生同士での集団にしておきたかった。5
折しも、私には思い当たる友人がいた。
彼は私と同じく先生の授業がきっかけで和歌(というか短歌だが)を詠み始め、大学に入ってからもインターネット上で私と時折歌のやり取りをしている高校の同級生であった。
今は関西圏で進学して大阪の大学生だという。丁度いいではないか。そう思った私が彼を誘い、ここに和歌詠み部(仮称)が誕生したのであった。6
和歌詠みのススメ
かくして私は彼と共に和歌サークルを結成し、今に至る。
その後、部員が若干増えたり「和歌」は長らく投稿されない時期があったりと色々あったが、今は一桁人数でささやかながら活動しているのが実情である。
実際の活動内容や、春の対面企画についてはこの連載記事の第三弾「和歌詠みのススメ #2・宣伝」で掲載する予定であるのでしばし待たれよ。
次回の記事では、「和歌読みのススメ#1・本編」を投稿する予定である。内容は、タイトル通り和歌の魅力やその詳細を語る予定である。
- 高校生の期待する思いを幼心と呼ぶのは無理があると思った読者諸君よ。私もそう思う。 ↩︎
- これは、テスト時間の最中に和歌を編み出さねばならぬから、なかなかに難しかった。ワンドロならぬワンヨミをやっていたわけなのだが、一方では「テーマを与えられる方が、無から詠むよりはまだ易しいな…」とも思える。実力テストの折には、たぶん紀貫之の日記の帰還の場面の文章で、二首ほど詠んだような記憶がある。 ↩︎
- ちなみにこの高3・受験直前期には、図書館部(仮称)の部員になっていたり季節外れの生徒会活動をしていたり(春先まで)、通称ホワイトボード部に仮入部員として入り浸ったりしていた。 まあそんなこともある。 ↩︎
- そしてそれがまた、大学及び大学での課外活動・有志組織のいいところでもあるのだが。 ↩︎
- 国家の三要件
・領域(国土、領海等)
・人口(国民)
・主権(政治体制)
サークルの三要件
・活動内容(活動実態)
・人々(部員・サークルメンバー)
・あと一つは?:「サークルであるという自覚」
↑自称すればいいのです。 ↩︎ - 誘った、という言い方に語弊があるのならば「二人だけのLINEグループを作成して無断で放り込んでは、活動内容の提案を矢継ぎ早に送り付けた」と言い換えてもよい。その後、この御仁の提案で新入生が入ってくる可能性もかんがみて匿名性の高いdiscordサーバーに移行、和歌詠み部の運営・会議の主軸はLINEからdiscordに移っていくことになるのだが……
まあ、それでも今なお故地というやつではあるのかな……。 ↩︎




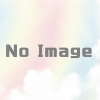
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません